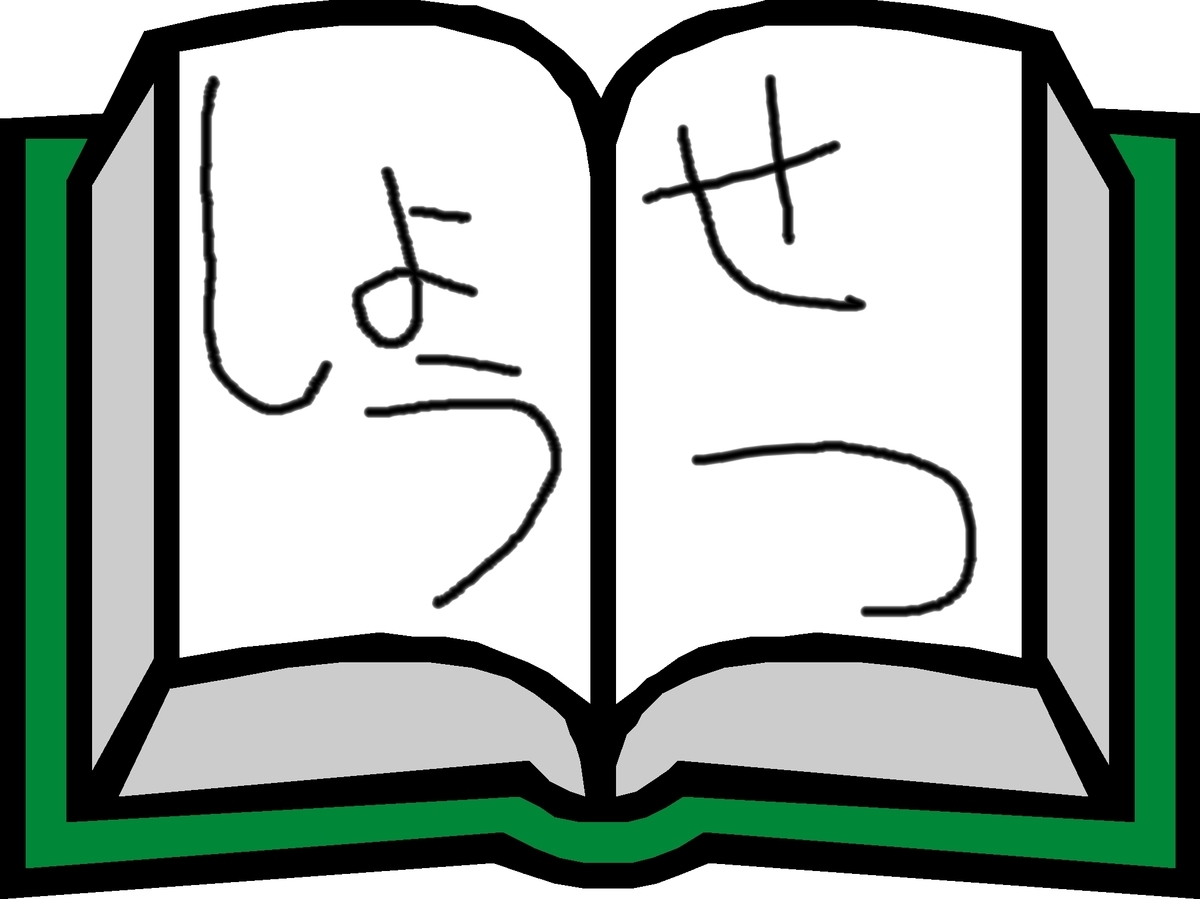
私は、インターネットの投稿サイト「ライターズクラブ」に小説を投稿している。今までに20以上の作品を投稿しているから、常連と云える部類である。他人が投稿した作品に、感想のコメントを寄せることも、よくある。そこでは一応、批評めいたことをするわけだが、私自身は、正直なところ本をまったく読まない。小学生の時分、夏目漱石の「坊っちゃん」と江戸川乱歩の「怪人二十面相」を読んだ覚えがある。記憶が確かなら、後にも先にも、私が完読しえたのはその二冊きりである。
私は当時、雑居ビルの夜間警備員の仕事をしていた。セキュリティーの総合会社に勤務していて、社内で、現金輸送も私服も内勤も経験したが、ビル管理の夜勤は初めてだった。夜勤を始めてみて、前任者たちが異動を拒み続けてきた理由が私にも判った。ビル管理ほど楽な仕事もない。見回りの時間以外は総て余暇時間のようなものである。
私は管理棟にある監視カメラ用に据えられたパソコンのひとつでネットサーフィンをはじめた。管理棟の仲間たちは、パソコンに疎い高年者ばかりである。およそどんな不埒なサイトを巡回したところで、履歴からそれを咎められる、という心配はない。しかし、私とて、勤務中に卑猥なものは見たくないから、もっぱら、夜長をやり過ごせる暇つぶしのサイトをさがしていたわけである。そこで見つけたのが「ライターズクラブ」だった。
自分の書いたものが晒され、様々な人たちが批評や感想のコメントを残していく。それを読むのが楽しい。また誰かの批判コメントに反旗をひるがえし、けんけんごうごうの言い争いに発展するのも、また楽しい。
棟内でパソコンがらみの仕事ができるのは私だけだったし、パソコンに向かってキーボードを叩いていれば、具体的に何をしているのかはわからないにしても、機械音痴の長老たちの目には、熱心に仕事をしている、と見えるらしい。そこで私は、心おきなく小説を書き続けることができたわけである。
私の文は、マンガやアニメーションからヒントを得たものを活字にする作業である。それが小説といえるのか判らないが、ハンドルネームだけで投稿できるインターネットの投稿サイトでは、案外渡り歩けるものである。渡り歩けるどころか、場合によってはいっぱしの文芸談義をぶつこともある。匿名という名の覆面をかぶったインターネット上の文壇では、たとい「坊っちゃん」と「怪人二十面相」しか読んだことがなくても、それを明かす必要はない。しかも、私は高卒で、とりわけ国語や現代文を得意としていたわけでもないのに、サイト内では一家言ある論客のひとりと見なされているのだ。
類型的にくくると、私の文は、人気作家であるY氏の模倣である。
私はY氏の本を読んだことはないが、氏の原作をマンガ化したものを読んだことがあって、きっとそれに影響を受けたのだろう。
私の理解する限りでは、主語と動詞だけで伝えられるはずの情景に、横文字を頻用した情報と、ひたすら余計なディティールをくわえると、Y氏の世界ができあがる。
たとえばこんな感じだ。
「彼女が西麻布のレストランで、アルバイトのウェイターのマニュアルトークに勧められるままに、南仏産の仔牛のテリーヌと真鰺のカルピオーネを注文していたとき、僕はアパートのベランダに無理矢理しつらえたつり床で、サリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」を読み終えるところだった。」
結局「僕は本を読んでいた」という状況を、魅力的なディティールを附加することによって、文学的にするのだが、ただし、この「魅力的な」というのは、Y氏の文学を愛する人たちにとって魅力的なのであって、万人にとって魅力的というわけではない。
私とて、西麻布だとか南仏だとかサリンジャーだとか、有産階級の愛してやまない小道具を散りばめることに、鼻持ちならない嫌忌を感じるのだが、それを読んで楽しいと思う人たちがいるのだから仕方がない。
「ちょうどその時、FMラジオから、鉄管を打つ音と、汽笛が聞こえ、ピアノの前奏が始まり、瞬時にB・ジョエルの「アレンタウン」だとわかって、御機嫌になったのだけれど、同時に、それをかき消すようなけたたましさで電話が鳴ったので、僕は、電話の相手に、今僕の大好きな曲がかかりはじめたところなのに、どうして今?と、食ってかかりかねない勢いだったのだけれど、それが彼女からの二回目の電話だった」
Y氏の作風の二番目の特長は「同時発生」である。すなわち、何かがおこった時、時をおなじくして、違う何かをおこさずにはいられない。
主役若しくは準主役が、印象的なセリフを言ったと同時に、電話が鳴る、FMラジオから印象的な曲が流れだす、というようなクサい演出が堂々と頻出するのはもちろん、主役が何かをなしえた時には、必ずどこか違うところにいる準主役も何かをなしえている、その二つの場面が、あたかも初期のブライアン・デ・パルマのスプリットスクリーンを見るかのように、同時進行で描かれるのである。
エッセイのなかで告白しているのだが、そもそもY氏が小説家になることを天啓のように決意したのは1981年の天皇賞で、その年引退するサクラギハイセイコが京都の第四コーナーを回って馬群から一気に先頭に躍り出た瞬間だったという。
その世界観にもとづき、なにかがおこったとき、それは必然として自分に関係する。すなわち同時におこる。
とりわけ小説の冒頭は絶対にこの手法で始まる。
「彼女が西麻布のレストランで、アルバイトのウェイターのマニュアルトークに勧められるままに、南仏産の仔牛のテリーヌと真鰺のカルピオーネを注文していたとき、僕はアパートのベランダに無理矢理しつらえたつり床で、サリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」を読み終えるところだった。」
私としてみれば、都心のアパートのベランダに、大人が横になれるつり床(ハンモック)が吊れるかどうか、ということを想像してみるだけで、この一文にいかがわしさを感じるのだが、このようなディティールがウケてしまうのだから仕方がない。
また、西麻布というのはたんなる場所としての情報に過ぎないわけだが、このような都会を志向する文学のなかで使える場所というのは、かなり限られていて、どこでもいいというわけではない。青山でも六本木でも可であろうが、上石神井や鶯谷では駄目だ。作中小道具のFMから流れだす楽曲も無論、何でもいいというわけではない。R・ストーンズとかA・フランクリンなら可かもしれないが、オリビア・N・ジョンとかF・イグレシアスでは駄目だ。
登場する主役は、たいてい都内の大学を卒業して、デザイナーかフリーライターか、そんなどこか雲を掴むような仕事にたずさわっているスノッブな青年で、読んでいる本は絶対にサリンジャーで、伊勢丹へ行くと絶対に薔薇の花束を買う。成城か、最悪でも柿の木坂に住んでいて、窓から野良猫が侵入してくることを、そんなに深刻でもない悩みとして、毎回のように彼女に打ち明けるのが特長といえば特長といえる青年である。
Y氏の世界がもつそれらのひとつひとつのディティールに、何故そうなのか?と、疑問に感じはじめたら、それこそキリがない。Y氏の文学を愛する人たちは、総体としてY氏の世界が好きなのであって、ひとつひとつの事象に、動議付けをすることはないがゆえにその世界を愛せるのである。
Y氏の作風の三番目の特長は「形容がまどろっこしい」である。比喩が複雑である、ともいえるが、とにかく、何を喩える場合でも、まどろっこしい形容を用いるわけである。こんな感じだ。
「僕が部屋に入った時、彼女は、子供の頃に貰った古いアイドルの、黄ばみ色褪せて、そこに書かれた黒マジックのサインが、ぜんぜん意味を為さない子供の落書きみたいに冴えないのに、なぜか引っ越しのたびに持って行かざるを得ない義務感を感じる色紙のように、部屋の片隅に両膝を抱えてうずくまっていた。」
部屋に入ったら、彼女をそこに見出した、という描写をするだけでこの有様だから、読むのにも骨が折れるだろうが、Y氏文学のファンはその読みにくさをかえって喜ぶようなマゾっ気を持ち合わせているのかもしれない。
これらの三つの皮相的な特長を真似て、日常の風景を綴っていくと、まさにY氏風としか云えないようなものが出来上がって、それを投稿すると、当然、Y氏風だと揶揄されるわけだが、私はそれにあらがって「この作風をはじめたのはY氏よりも私が先だった」と言い張ってみることにしている。確認とか検証のやりようがないことを主張すると、論争が泥沼化しやすいことを知っているからだ。論争は泥沼化したほうが面白いし、インターネットのなかでは、虚言や大言壮語を吐いても、後ろめたさがない。相手を憤らせる発言は、私の得意とするところだった。
その後、社内異動があって、私は再び日勤に戻った。都心の、俗に億ションと呼ばれるマンションの管理で、パソコンは無く、終日人目にふれる玄関近くにいるため、マンガ本を読んでいるわけにもいかない。
そこで私はついに本を読むようになった。私は小さい文庫本をいつでも携帯し、暇さえあれば頁を繰っている。
パソコンを持ち合わせない私は、小説の投稿はおろか、インターネットを閲覧することもめっきりしなくなったが、それでもたまさかパソコンに触れる機会があると「ライターズクラブ」を訪れる。
本を読むようになってから、自分で何かを書く意欲は失せたので、もう投稿してはいないが「ライターズクラブ」は、尚も、十年一日のごとく、続いている。
しかしそこに集う人は変遷していく。結局、いずれ現実が、いやおうなしに人を、その人の能力相応の仕事や生活に向かわせるということなのだろう。